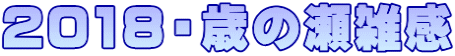 2018-12-20 Web編集:独法師 |
||||
|
皆さんお久しぶりです。お元気でしょうか。 2018年の夏は記録的な豪雨、たびかさなる強烈な台風、そして強い地震に襲われ多くの犠牲者がでました。連日の猛暑に悩まされもしました。この異常気象は日本のみならず世界的な規模でおこっています。なにか地球滅亡を予感させるような不吉な気持にさせられます。新元号にかわる来年こそは、穏やかな良い年になることを期待しています。 ところで、僕はこの10月で79歳になりました。80までもう少しのところまで生き延びました。そこで頭に閃くのは人間80年というのは、そろそろ死に支度の時代にはいったということです。ところが自分ではそんな深刻な感覚がなく、なんとなくボゥーと生きています。どうやらチコちゃんに叱られそうです。 年齢を重ねるにつれて、何をするにも億劫になった気がしています。朝起きて顔洗うのさえ面倒くさくなっています。人と会うのも、気を使うので疲れてしまう。外出するのも億劫になってきました。この、ちょっとした“億劫さ”が認知機能を低下させるようです。なんだか怖い話ですね。 「老人劣化しやすく、されどポックリ逝きがたし」 さて「年の瀬雑感」は今年で7年目になりました。老いの戯言に過ぎない、相変わらずの駄文にお付き合いさせて、申しわけなく思っています。 文章作成は結構なエネルギーを使います。まして筆不精で日ごろから文章を書く習慣がない僕は、拙い雑文とはいえ悪戦苦闘します。このごろはものを書くことが、ますます億劫になってきました。このへんで筆を置こうとする誘惑にかられます。 しかし、褒めすぎと思える感想を寄せてくれる人が、一部にいます。このほめ殺しのおだてにのせられ、単細胞の僕は気をよくして、老体を鞭打ってパソコンの前に座ってキーボードを叩いています。 孫娘2人が国立劇場で琴の演奏! 冒頭のタイトルに驚いた方がおられよう。それにはある事情があった。ネタをバラせば「なぁ〜んだ」と言うことになるだろう。 妻は20歳後半から半世紀近くにわたって、琴を人生の趣味としている。師匠は山田流山木派6代家元山木千賀師である。家元には幼少のころから琴を教えていた娘がいた。彼女は成長し、東京芸大大学院邦楽科に学んだ。そして今では新進気鋭の若手の筝曲演奏家の一人として多方面で活躍している。家元は山木派200年記念を節目として家元の席を娘に継承した。 そして11月7日国立劇場にて山木派200年記念演奏会・7代山木千賀襲名披露が行われた。当日は特別出演として山勢松韻師、米川文子師、富山清琴師、山彦千子師の人間国宝の演奏があり、賛助出演に生田流、山田流の重鎮の演奏があった。特に人間国宝4人が顔をそろえるなどめったにない。かなり格式の高い盛大な演奏会であった。 この演奏会に6代目の孫つまり新家元の息子3歳が、初舞台を踏むことになった。その共演者として、3歳と5歳の僕の孫娘二人ともう一人5歳のお嬢さんに白羽の矢が当った。なんとまあみんな幼児。それがいきなり国立劇場の大舞台に立つのだから、無謀ともいえる仕業である。 今年の中ごろから、妻は孫たちに演奏会に向けての稽古を始めた。しかし、正座して、180cmもある木の箱に張られた13本の弦を、小さな琴爪で操るのは極めて難しい行為であった。練習は思うように進まず、妻をハラハラさせていた。演奏会3か月前に着物ができ上った。「これを着て舞台にでるのよ。しっかりとがんばってね!」と母親に諭されて、5歳の孫は責任を自覚したようだ。それからは熱心に稽古に励んだ。3歳の孫もお姉さんの真似をしてやる気を見せている。リハーサルはスケジュールが合わず4人でそろって演奏したことがない。ぶっつけ本番とはこのことだ。いろいろ不安を抱えながら、当日を迎えた。 僕はこれまで演奏会に行ったことはなかった。自宅では妻の琴の音を、しょっちゅう聞いている。また弟子たちの「おさらい会」を見ているので、ことさら演奏会に行こうとは思わなかった。だが、今回は孫の出演とあっては見逃すわけには行かない。久々に気合が入った。演奏会は午前11時から始まり終焉は午後9時とかなり長時間におよんだ。 孫たちの出番は12時過ぎである。曲目は童謡曲のキラキラ星とユーリップ。司会者より曲目が告げられた。会場は一瞬静粛し、そしてしずかに幕が上がった。壇上に登場した4人はなんと堂々としている。そしてあたりを見渡し、しずかに頭を下げた。立派である。5歳の孫は半月前にピアノの発表会があり舞台慣れしている。3歳の孫は誕生日を迎えたばかり。ついこの間まで、人見知りが激しく母親から一時も離れなかった。その子が大舞台に座っている。爺さんはびっくりした。感動した。演奏時間はたったの3分間であったが、4人とも見事に唄い合奏しきった。 ♪ さいた さいた チュリップの 花が ならんだ ならんだ 赤 白 黄色 どの花みても きれいだな ♪ ****************************************************** ♪ きらきらひかる おそらのほしよ まばたきしては みんなをみてる きらきらひかる おそらのほしよ ♪ 観客は目を細めて大喜び。やんやの大喝采であった。「どんなにうまい役者でも可愛い子供と、動物にはかなわない」とは言いえて妙である。 一門として妻とその弟子も参加している。演奏会の曲目は32。そのうち5曲が妻の出番であった。国立劇場にはたびたび出演しており、会場は慣れているはずの妻がかなり緊張している。この世界では超一流の芸大教授との共演とあれば、身が引き締まるのは当然だろう。日ごろの研鑽の成果が試されているのであるから。 プログラムは次々と進んでいく。ともかく、一芸を極めた人たちの演奏は圧巻であった。なかでも人間国宝の方々の、年を感じさせない凛としたたたずまい。そして、楽器と対峙する姿。それはあたかも、剣豪が真剣勝負を挑むような凄みすら感じた。 ちなみに人間国宝とは、重要無形文化財である伝統芸能や伝統工芸の分野において歴史的・芸術的に価値の高い“わざ”を持っている人が国から認定されて重要無形文化財保持者になり、人間国宝と呼ばれている。正式な定員数というのは確認できないが、2017年7月に文化庁から出された報道発表によると、認定指定数は116人だそうだ。特別助成金として国から年額200万円が支給されている。(ネット検索より) 琴の調べは、西洋音楽にはない和楽特有の雰囲気を醸している。その繊細で美しい音色は実に多彩で豊かであった。そして、日々の疲れを癒し、心和らぐひと時をあたえてくれた。長い曲では15分を超える演奏時間がある。僕は演奏が始まり、しばらくすると睡魔におそわれ、よく眠っていた。気がつけば睡眠不足を、解消しに来たようなものであった。それほど居心地の良い空間であった。日ごろは、妻の弾く琴の調べに関心を示さなかったが、これからはヒーリング音楽として不眠症の改善に役立てようと思ったりした。 わが母を語る この秋、樹木希林さんが亡くなった。その追悼映画として井上靖の「わが母の記」をTVで放映していた。この映画は2012年モントリオール映画祭でグランプリを受賞し、世界を感動させた傑作で希林さんの熱演が光っていた。映画を見ながら僕は17年前に世を去った、わが母の面影を追い求めていた。 母の父、つまり僕の祖父は島根県松江で旧制中学校の教師をしていた。母は大正元年に父の赴任先で生まれた。名前を「松枝」という。これは生まれた土地に由来している。七人兄弟の長女であった母は6歳の時に、子供のいなかった叔母夫婦のもと(現在の僕の実家)に養女となり、可愛がられ大事に育てられた。長じて地元の女学校を卒業し、さらに東京の学校に学び教員の資格を取った。そして地元の女学校で教師を勤めた。やがて、父を婿養子に迎え3人の男の子をもうけた。その次男が僕である。 時は戦中戦後の激動期。なに不自由なく暮してきたお嬢さん育ちの母に、大きな試練が訪れた。それは、夫すなわち僕の父の満州出兵と戦後のシベリア抑留であった。抑留者の引きあげがはじまったのは、終戦から1年以上が経過した1946年の12月から。父は2年を超える抑留生活を送った。マイナス30度にもなる極寒地で、十分な食事を与えられず栄養失調に陥る者が続出したという。「これがロ助にこん棒で殴られた傷跡だ」と髪をかき分けて古傷を見せてくれた父。だがそれ以外多くを語ることはなかった。おそらく寒さに耐え、重労働、そして仲間の死など思い出したくなかったのだろう。 母は、育ちざかりの3人の子を抱え、必死に生きぬいた。慣れない畑仕事もした。さつま芋の買い出しに、朝早くから出かけることもあった。身の回りの衣類・家財などを少しずつ売って食いつないでいくタケノコ生活もした。ともかく、米はなく、代用食としてさつまいもやじゃがいも、すいとん、草殻、もち草、サトイモやかぼちゃなどの葉や茎まで、あらゆる食べ物を食べて生き抜いてきた。僕たちはいつも空腹をかかえていた。そんな中、頼りにしていた義母が脳卒中で倒れた。学校の勤めもあり、介護もしなければならない。母の苦悩はますます深まった。 戦後の食糧難はけっして我が家だけではなく、多くの日本人が経験したことではある。が、しかし戦後GHQの農地改革で、ただ同然の値段で地主から土地を購入した小作人は、白い飯を鱈腹食っていた。羨ましかった。 そして、母の苦境を救ってくれたのは、父の帰還であった。父は髭ぼうぼうの憔悴した姿で我が家に帰ってきた。出兵前の姿はおぼろげながら覚えている僕は、これがわが父なのかと、好奇の目で見つめて、父の帰りを素直に喜べなかった。体力の回復には時間がかったものの、やがて高校の教師に復職し母の重荷は下りた。 母は生活も安定したころを見計らって退職した。それからは専業主婦となり平凡ではあるが、穏やかな日々を送っていた。 時は流れ、晩年の母のことを語ってみよう。 晩年の母は父とともに、家庭菜園、花の栽培、俳句や旅行など老後を楽しんでいた。そんな円満な老夫婦の姿は子供にとっても愉快なものであった。僕は一人娘が小さいときは、よく実家を訪れた。母は孫娘の手を引いて隣近所や親せきを自慢げに回っていた。このひと時が母の至福の時間であったのかもしれない。それでも娘が大きくなると、実家訪問はだんだん疎遠になった。 母は80歳近くなり、うつ病が発症し炊事・洗濯・掃除など家事全般ができなくなってしまった。母の父は教育界で活躍していたが晩年は、家に閉じこもりがちで、近所の人が訪ねてくれば付き合うものの、己から進んで人と交わることを避けていた。隠遁生活者のようであった。母もその血を受け継いでいるので晩年が心配であった。ちなみに、僕は母方の遺伝子が強いようで、ものごとを悲観的に考える、ペシミストの傾向がある。その一方、楽天的な父方の血も多少ミックスされているようだ。 ある日、母は古井戸に飛び込み自殺を計ったそうである。幸い父が見つけ、事なきを得た。「もう少し遅れたら、お陀仏になるところだったよ!」と楽天家の父は半分おどけた口調で、大騒動の顛末を話してくれた。 父は心を尽くして母を看病した。苦労の甲斐があって母は次第に気力をとりもどし、一緒に台湾旅行に行くほど回復した。僕は父と電話で母の様子を聞いていたが「心配することはないよ。わざわざ来なくていいさ」が口癖であった。 ある秋のこと、高校のクラス会で久しぶりに実家を訪れた。 母は布団にくるまって静かに横たわっていた。僕が「元気かい」ときくと「よく来たね。お前達も元気かい」とか細い声で囁いた。小さくなった母の姿が哀れであった。母にはずいぶん苦労をかけたのに、父のいうことを鵜呑みにして、母の病状が進行を気付なかったことを後悔した。 実家には独身生活を謳歌している同居の兄がいる。近くには弟夫婦が所帯をもっている。それなのに、なぜ母の面倒を見てくれなかったのかと、責め立て激しく面罵した。兄たちは「たまに顔をだして偉そうなことを言うな。俺たちだってそれなりに気を使っているのだ」と兄弟が険悪な事態になった。取っ組み合いの喧嘩になりそうになった。でも冷静になって考えると、徐々に弱ってきた母の変化は、身近にいる兄たちには、案外気が付かないかもしれない。また、うつ病は感情の起伏により症状に変化があり、たまたま僕が、最悪なときに巡り合ったのかも知れなかった。 ともかく、このまま放っておくわけにもいかず、翌日、病院に連れて行った。医師は入院治療をした方がよいといい「リハビリセンター」を紹介してくれた。早速センターに出向き入院のお願いをした。センターの担当者は「病院の診察結果がでるまでは入院できません。おそらく5,6日先になるでしょう」とのこと。 僕はまだ現役で仕事を持っている。何日も会社を休むわけには行かない。かと言って、兄や弟にまかせてしまうのは気がかりだ。そこで施設長に事情を話して、本日から入院させて欲しいと懇願した。施設長はしばらく考えていたが、やおら席を外した。どうやらベッドの空き具合や直接介護を担当する人たちの了解を取っていたようである。ほどなくして戻ってくると「入院が決まりました。私たちが引き受けたからには、お母さんを元気な身体にして家庭復帰させますよ」との心強い言葉をいただいた。施設長は50歳前の理知的な顔の美人で、そのときの彼女は女神のように輝いて見えた。施設長の浅野さんの名前は今でも忘れない。 それからは足繁く母のもとに見舞いに訪れた。道すがら母と同じくらいの年恰好の老人が、生き生している姿が気になった。母も早くあのように元気になったらよいものと、願掛けた。見舞いはいつも父と連れ立って、ひとしきり、世間話をして母を元気づけた。母は父の冗談話にも乗り気がなく、なんとなく元気がなく鬱々として覇気がない。それでも父や僕の顔をみると、ほっとした安らぎの表情を見せるのである。 母は呆けているわけではない。あるとき父が、遠い親戚に不幸があったことを伝えると、あの家からは義母がなくなった時に香典をもらっているので、ちゃんとお返しをして欲しいと父に指示をしていた。母は記憶力がよく昔のできごと明瞭に覚えている。 しかし、早く良くなろうとする気力が弱く、苦しいリハビリを熱心にすることをしなかった。リハビリセンターには2年間療養したものの、加齢も手伝って、だんだん心身が衰えてきた。そしてある日、施設長から「私たちも精いっぱい努力しましたが、お約束の家庭復帰を果たすことができず心残りです。これからは”特別養護老人ホーム”で療養されることをお勧めします」と挫折感をただよせながらの説明があった。その上で、特養を紹介してくれた。特養は入居待機者が多く数ヶ月以上待たされるのが普通だが、施設長の計らいですぐに入所可能になった。九十九里海岸近くにある"特養"は、極めて環境の良い場所にあった。 そのころ、父は87歳の高齢になっていた。僕は会社の役職交代制度を利用して定年を待たず、実家で父と暮らすことを決意した。 そんな折、一冊の本に出合った。舛添要一著「母に襁褓をあてるとき」(襁褓=むつきとはオシメのこと)。そこには舛添家の介護の実態が赤裸々に描かれていた。あれほど多忙に生きている舛添氏が、東京から九州まで週末ごとに通った、遠隔介護の話は僕を感動させ、何やら元気が湧いてきた。埼玉から千葉に通っていた僕など、まだまだ努力が足らないように思えた。 ところが、のちにこの作品は虚偽であるらしいとの噂が流れた。舛添氏が「母親のオシメを替えている姿など見たことはない」と身内から反発がでた。でも、親の介護をめぐって兄弟姉妹間の確執がおきるのは当たり前のこと。真相は不明だが、あれほどリアルな体験記は嘘で書けるはずがない。 実家に帰った僕は極力、"特養"に通い母と過ごす時間を多くした。父も母を見舞うことが楽しそうであった。そのころの母は足腰が弱って、自力で歩行は困難になっていた。そこで、車いすで園内を散策した。また、少し離れたところまで足を延ばすこともあった。九十九里浜の潮風をうけ、母は満足そうな微笑みを浮かべる一幕もあった。 しかし、このような日々も長くは続かなかった。"特養"には5年間お世話になったが、後半の3年間はほとんど寝たきりの状態が多くなってしまった。下の世話は無論のこと、食事は介護士が車いすで食堂に連れて行き介助していた。僕は子供のころしてもらった時のように、今度は母のオムツを替えてやろうとした。だが、母はかたくなに拒否した。それは、子供に迷惑を懸けまいとする、親心と僕は受けとめた。 母と同室で隣にいる老女は、意識がなく口を半開きにしたまま、鼻の穴から食道や胃にチューブを通す「経鼻経管栄養」で命を繋いでいる。母をこんな状態にしたくないと思っていた。 そしてついに最期のときを迎えた。母の様態がおかしくなったとの知らせに、すぐにかけつけた。そのとき母はこと切れていて、最期を看取ることはできなかった。枯れ木のようにやせ細った哀れな姿に、長い間ご苦労さんと合掌し涙した。 結局、母は再晩年の7年間を施設生活に明け暮れた。それは幸せであったのか。認知症で脳が破壊していれば、夢の世界に生きる事もできたであろう。しかし、最後まで頭のしっかりしていた母はどんな気持ちで、日々を送っていたのか。冥土の母に聞いてみたい。母の身体が正常なときに親孝行が十分できなかったことは、今でも自責の念に駆られている。 父は健常で90歳を過ぎても足腰が丈夫で2階に起居していた。2階からあたり一帯を眺めて、道行く人の様子や隣近所の動向を観察していた。新聞を読み、TVを観賞し、好奇心旺盛で案外の情報通であった。ある朝、食事時になっても下りてこないので父の様子を見に行った。すると、ベットに座ってぐったりしていた。病院での診察結果は脳梗塞であり、直ちに療養生活に入った。 2001年の梅雨明けは例年より早く、7月初めに雨が上がって夏が訪れた。ある夜、父の危篤の知らせが病院から届いた。僕たち兄弟はすぐ病院に駆けつけた。そのとき、父はすでに意識がなく会話ができる状態でなかった。当直の若い医師は「私たちは手を尽くしました。後は本人の生命力を待つしかないでしょう」という。当直医はなにやら頼りない。主治医は明日の朝に出勤されるとのこと。主治医なら助けてくれるかもしれないと、一抹の期待を寄せた。 普段は両親とのかかわりが淡白であった兄が、父の足を朝まで休むことなくマッサージしている。マッサージがどんな効果があるのかわからないが、そうすることで悲しさをまぎらせようとしているようだった。 翌朝、主治医が来た。主治医は直ちに輸血を始めた。一瞬父の回復を期待した。が、それもつかの間、午前9時50分臨終を告げられた。入院は1年でピリオドをうたれた。 昨年暮れ、両親17回忌、兄7回忌、そして弟の3回忌を実家の檀家寺で行った。実家の墓は子供のいない、弟の細君が墓守をしている。 2001年02月12日 母死亡 享年90歳 2001年07月13日 父死亡 享年93歳 2011年11月11日 兄死亡 享年74歳 2015年03月12日 弟死亡 享年72歳 母は2月に死亡したが、入院中の父には知らせなかった。父は7月に母の後を追うようにこの世を去った。両親は長命であったが、兄と弟は比較的短命であった。僕はあと何年生き延びることになるのか
|
||||
|
ナミビア再訪の旅 10年ほど前に行った、南アフリカ・ナミビアを思い出した。そこにはアプリコット色に輝くナミブ砂漠の感動的な光景が広がっていた。冥土の土産にあの大自然の絶景をもう一度眺めてみたい。そんな衝動にかられた。歳を重ね足腰が弱り長旅はきつく、これが最後のチャンスになるかもしれない。 旅情報を集めようとネット検索をしていたら、U社の「ナミビア大周遊と砂漠の花園ナマクワランド 13日間」がヒットした。早速申し込んだ。このツアーの見どころは、荒涼とした砂漠地帯に、一年のうち7,8月ごろの一時期、一瞬だけ花が咲き乱れる奇跡の花園ナマクワランドであった。このためツアーは人気が高く、参加者は18名の大所帯となった。 8月14日、成田空港に向かった。 前の日から2日ほど孫たちと新潟の「あてま高原リゾート」に避暑をしていた。ところが皮肉なことに台風の通過によるフェーン現象で、北陸は39度以上の熱暑に見舞われ、避暑どころか東京より暑いところに、わざわざでかけてしまった。加えて日本列島の異常な猛暑に体力を消耗している。これからの長旅が思いやられる。一抹の不安を感じながらの旅立ちであった。 香港、南ア・ヨハネスブルグ経由でナミビアの首都ウイントフックへ向かった。香港からヨハネスまでの国際線は、パーテションで仕切られたフルフラットの座席を選んだものの、通算18時間のフライトは厳しい道のりであった。そして、エトーシャ国立公園近郊の宿泊地までは大型バスで6時間。未舗装の悪路をひたすら走る。成田を立って2日間。やっとツアーのスタート地点に到着した。 エトーシャ国立公園ではインパラ、キリン、象など過酷な条件下で必死に生きる野生動物を観察した。そして、ヒンバ族の村、ブッシュマンの岩壁画、荒涼とした月面を連想させる「ムーンランド・スケープ」、クイセブキャニオンなどを見学しながら旅は進んでゆく。ともかく毎日移動距離が長く、老体には過酷な日程であった。 ツアー6日目、いよいよ僕の主目的であり憧れの地、ナミブ砂漠の観光である。早朝6時にロッジを出発する。ゲートのオープンと同時に、デューン45を目指す。300m級の世界最大と言われる砂丘群の中でも「デューン45」は、砂丘のシェイプが最も綺麗なものとして世界的に有名である。太陽の高さの低い午前中は、砂丘にできる日陰のコントラストが美しい。僕は夢中でカメラのシャターを切った。 その後、4WDに乗り換えナミブ砂漠の最深部「デッドフレイ」に向かった。デッドフレイとは、ナミブ砂漠の一角に存在する、“死の沼”と呼ばれる枯れた沼地である。かつて川の洪水で形成された沼地が、気候の変化によって水が干上がり、木々は立ち枯れ、その後1000年もの間“死の姿”を留めている奇跡の絶景ポイントだ。ひび割れた白い地面に1000年前に枯れた無数の木々が、そのまま残っている。絶景ポイントまでは、車を下りて緩いのぼり道を歩く。10年前は簡単に歩けた道のりを、ハァハァあえぎながら、やっとの思いで登り切った。10年の歳月が僕の肉体を確実に劣化させていた。デッドフレイは、昔とほぼ同じ形で静謐な時を過ごしている。 早朝からハードなスケジュールをこなし肉体的には疲労困憊していた。しかし、思い描いたアプリコット色と形容される美しい砂肌を十二分に堪能し、満足感に浸った。このことで肉体は疲労しているものの、気分的には元気いっぱいであった。そして、夕食はワインを飲みながらツアー仲間と遅くまで談笑した。 しかし病院の診断を受けるためには、ツアーから離れて単独で動かなくてはならない。通訳をつけるとしても日本語のできる人は望めない。若い時には片言の英語を頼りに、見知らぬ他国を一人で旅したこともあったが、今ではそんな気力や体力もない。第一、日本語の会話も覚束なくなっている。とても一人で行動する自信がない。 まだ旅のスケジュールは半分も終わっていない。これから先のことを考えると、不安が高まり心臓は激しく鼓動している。このまま旅を続け良いものか。戻らなくてはならないのか進退窮まった。パニック状態となり冷静な判断ができない。その時、添乗員Tさんから「日本に電話して主治医と相談したらどうですか」と言われた。 僕は、3年前に日赤大宮病院で心房細動の根治的治療としてのカテーテルアブレーション手術をうけた。担当のI先生には、今でも定期的に検診に行っている。I先生は僕の心臓を熟知している信頼できる名医である。 現地と日本の時差は6時間。日本は午後3時。先生に緊急の手術が入っていなければ、対応してくれるはずだ。「こちらはアフリカのナミビアから電話しています。I先生と緊急に連絡を取りたいのです」祈るような気持ちで必死に電話をかけた。担当の看護師はアフリカと聞いてすぐに電話を取り次いでくれた。 まもなくして先生との電話がつながった。先生は僕に脈を取らせて、遠隔で問診をしてくれた。「脈の乱れがないので、疲労による一過性の頻脈です。高度の高い山に行かなければ旅行を続けて大丈夫です。」先生の言葉に安堵し急に頻脈が収まったように思えた。そして先生は、ある薬を処方してくれた。僕は先生にいわれた英語表記の薬の名前を一生懸命にメモした。その薬はBisoprolol Fumarate2.5mg(ビソプロロールフマレート)で心臓の動きを緩やかにする効果があるものらしい。 この国では医師の処方箋がなくても薬は自由に購入できる。でも、こんな田舎町に心臓の薬が置いてあるのか気がかりだったが、運よく薬が手に入りひとまず安心。薬は著効があり、その日のうちに頻脈は治まった。 こんな騒動で出発時間が大分遅れてしまった。ツアー客は男5名、女性13名。30代の若者も2名いたが、60歳〜70歳前半の人が大半であった。僕が最長老かと思っていたら82歳の女性がいた。皆さんは大変親切でツアーの遅れにたいして迷惑なそぶりを一切見せず、心から僕の体を労わってくれた。そして、バス移動では振動の少ない最前列の席をいつも譲ってくれた。青空トイレで「野ション」を余儀なくされる辺境の地を好んで旅する女性は、風の変わった人が多い。それでも心根は優しく、子供のような純粋気持ちを失っていない人が多いようだ。 旅行8日目。国境を越え南アフリカナマクワランド地方へ向かった。8月下旬から9月の南アフリカの春、ナマクワランド地方の荒野に野生の花々が一斉に咲き乱れ、地平線の彼方まで続く広大な花畑が出現する。わずか3週間の開花時期に合わせてこの時期、美しい奇跡の花畑を見つけようと「フラワーハンター」たちが世界中から訪れる。 旅の終わりはケープタウンであった。アフリカ大陸の南端に突き出たケープ半島。そこにはアフリカ大陸の植物の約20%が自生し、そのうち70%近くが固有種という南アフリカ原産の植物の宝庫である。なかでも、テーブルマウンテンの南側斜面に位置するカーステンボッシュ植物園は、南アフリカ共和国の国花で、花の王様と称えられる約100種ものプロテアが、華麗に咲きそろうプロテアガーデンは圧巻。僕たちは閉館間近の庭園を急ぎ足で見学した。 ケープタウンといえば、クリスチャン・バーナード教授によって世界初の心臓移植手術が行われた街である。とりわけ心臓に疾患のある僕は関心が強く、バスの窓越しに手術の行なわれたグルート・スキュール病院を、まじまじと見つめた。 バーナード教授は1967年12月3日に最初の手術を行った。患者は術後、18日目で死亡している。1968年に別の患者に対して2回目の心臓移植手術を行っている。その時の患者は、9カ月間生きることができたとされた。教授は、アパルトヘイト(人種隔離政策)の時代に、黒人から白人に心臓の移植を行ったため、黒人層からは「黒人の人命を軽視している」と非難されたこともあったが、現在では医療の進歩に貢献したとして世界的に高い評価を受けている。(ウイキペディアより) そして、迷惑をかけた旅仲間になにか謝礼をしようとしたが、「そんな心配は一切不要。明日は我が身のこと」と皆さんにたしなめられた。「人の誠は旅にて見ゆる」と諺にあるが、旅でうけた親切は、僕の人生の良い思い出となって回想することになるだろう。 だれが詠んだか知らないが、「落ちぶれて 袖に涙のかかる時 人の心の奥ぞ知らるる」ふとこの歌が頭をよぎった。これからは人の情けにすがって、生きることが多くなるかもしれない。恥を重ねないうちに、早くこの世を去りたいものである。・・・といいつつも長命を願ってしまう。 |
||||

